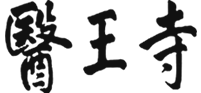霜ヲ履ンデ復陽ヲ思フ
地中の復陽といえば、冬至に一陽来復するというのも易経の説である。この地中に
来復した微かな陽が息(そく)して、2月の頃ともなれば二陽となるわけであるが、この地中に
深く微かに来復し息する陽を愛護し重陽するという考も易経に説いている。厳冬の時期
にすでに地下に陽が生じており、酷暑の時期にすでに地下に陰が生じているというよう
に、表面的・感覚的な現象の根本にあるものを捉えるという考は極めて東洋的なもので
ある。・・・・春になる桜の枝はなにとなく花なけれどもむつまじきかな とあるのは、
水分を盛に吸いあげて瑞々しくなった作粗の枝をめでているのである。桜を愛することの
深かった西行は普通の人が気づかぬ生気、瑞々しさを直観したのであるが、次の八木重吉
の「梅」と題する詩も同じところを感じとってゐると看得よう。
梅を見にきたらば、まだ少ししか咲いてゐず、こまかい枝がうすうすと光ってゐた
早春の雑木林にたつ生気に感じて活動している根を想うのであるが、詩人の直観と
易経的哲理の静観との相応・一致がここにある。(「東洋思想講座 古教照心」木南卓一著)
恩師である木南先生の著述から学ぶ東洋的自然観察は引用される古典とあいまって
自然観察の深さを教えられます。もう少しで二陽ですね。